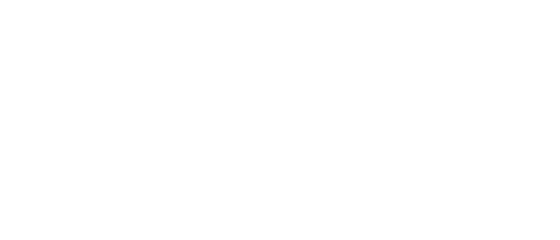おはようございます、ワン子だワン。
8月の半ば、つまりお盆の時期が来たワンね。
と言ってもお盆には「7月盆(新盆)」と「8月盆(旧盆)」があり、8月盆の方が主流なので一般的にはこの時期をお盆と呼びますが、7月盆が定着している地域や業界などでは1ヶ月早くお盆を迎えていたりするワン。
そんなお盆ですが、実際のところどういう行事なのか詳しく知らない人も居るんじゃないかワン?
なんとなく「帰省して親戚一同が集まる時期」みたいなぼんやりした認識の人も少なくないと思うワン。
そもそもこの「お盆」は仏教における「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という行事が由来で、その盂蘭盆会もサンスクリット語の「ウランバーナ(逆さ吊りの苦しみ)」という言葉が由来になっているワンね。つまり「お盆」という名前はサンスクリット語の当て字で、元々は日本語ではないということだワン。
※盂蘭盆会の由来については諸説あるが、いずれにせよサンスクリット語が由来とされている。
この盂蘭盆会という行事は「僧侶が集まって行なう『安居』という修行の最終日(7月15日)に供物を捧げることで亡き母を供養した目連尊者の逸話」に由来しており、これをそのままの日付で引き継いだものが7月盆、旧暦と新暦のズレに合わせて時期をズラしたものが8月盆と言われているワンね。
これにより現代のお盆は、僧侶ではなく親族が集まって先祖を供養する行事となった、というわけだワン。
だいたい鎌倉時代には一般庶民の間でも定着していたそうなので、現代まで800年くらいは続いていることになるワンね。
《続きを読む》