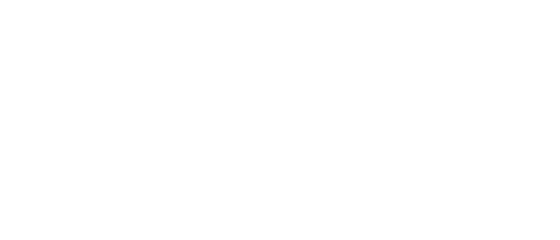小説「うみのあな」後編
カリハはそう言ってニヤリと笑みを浮かべると、その笑みを崩さぬまま胸元のチューブトップに指をかけ、躊躇いなく引き下ろした。当然、胸を隠している布を取り去れば、その下にある2つの乳房があらわになる。それは肌の白いセーラとは対照的な、まさしく真夏の太陽で日焼けしたような小麦色で健康的な乳房だった。
「な、なにを……!?」
「帰ってくるなりあんなもん見せられたら、こっちもその気になるってモンだろ? おまけにセーラがあんだけ乱れてたんだ、オマエもそこそこイイモノ持ってるってことじゃねぇか」
「イイモノって……あ、ちょっ」
「ほら、触ってみろよ。鍛えてっから腹は筋肉でガチガチだけど、胸はセーラにも負けない柔らかさだぜ?」
手首を掴んだカリハに引き寄せられ、俺は戸惑いつつ彼女の剥きだしになったおっぱいに触れる。確かにカリハ本人が言う通り、柔らかさはセーラにも負けていなかった。セーラのおっぱいがふわふわしたマシュマロだとしたら、カリハのおっぱいは柔らかくも弾力のあるゼリーと言ったところか。カリハには「触ってみろ」としか言われていないが、俺は無意識のうちに彼女の2つあるおっぱいを両手で掴み、夢中で揉み始めていた。
「んっ……! お、オマエも結構、その気じゃねぇか……!」
俺の指が乳首に触れると、カリハは分かりやすく体を震わせて反応した。寒いわけでもないのに、彼女の乳首はすっかり勃起して硬くなっている。それだけカリハも興奮しているということだろう。彼女が漏らす吐息を聞きながら、俺の興奮も高まっていた。
「んあっ、オマエ……触り方がやらしいぞ……!」
「こうした方が、カリハも気持ち良いだろ?」
「それは……っ、そう、だけど……んんっ」
指の腹で乳輪の縁をなぞってやると、カリハはさっきまでの威勢が嘘のように声を抑えてビクビクと快感を堪えているようだった。その様子を見ているだけで、俺はさっき射精したばかりの肉棒に元気が戻っていくのが感じられた。カリハもそのつもりだって言うなら、なにも遠慮は要らないはずだ。
俺は、この人魚と「交尾」したいと思い始めていた。
「なあ、カリハ。下も、触って良いか」
「下……? あっ、おい、まだ答えてな……ぁ……っ!」
カリハの下腹部、人肌が鮫肌に変わる境目の辺りにある割れ目からは、既に愛液が湧き出て滴り落ちている。胸への愛撫で彼女が興奮している証拠だ。カリハが返答するよりも先に俺は割れ目の中へと自分の指を滑り込ませたが、それを彼女が拒絶する様子はなかった。
くちゅくちゅと卑猥な音が響く。指を動かすたびにカリハは小さく吐息を漏らし、膣肉で俺の指を締め付けた。これだけ濡れていれば問題はないだろう。俺はセーラにぶつからないことを確認しつつ、海藻ベッドの方へとカリハを押し倒した。
「カリハ、入れるぞ」
「……ヘッ、アタシに絞り取られたいなら受けて立つぜ」
さっきまで余裕なく喘いでいた様子はどこへやら、カリハは気丈な態度で言い放つ。ならば受けて立ってもらおうじゃないか、こっちの昂ぶりもそろそろ限界だ。バキバキに勃起した男根を押し当て、俺はカリハの愛液にまみれた割れ目をこじ開けた。
「ぅあ、ぉ、んあぁ……っ」
「うおっ……すごい締め付けだ……!」
挿入しただけでイかされそうな、力強い締め付け。俺は、まるで獰猛な鮫に噛みつかれたような「逃げ場のない」感覚に襲われた。だが、カリハの方も余裕綽々という反応ではない。このまま一方的にイかされてたまるか、まずは俺がカリハをイかせてやる。
「動くぞ」
「良いぜ……かかってき、なぁ……っ!? あ、待っ、深っ……ぁ!?」
カリハの穴の奥の奥、男根が根元まで飲み込まれるように俺は腰を押し付ける。深い場所に亀頭がぶつかると、カリハは大きく仰け反るように反応を示して悲鳴のような喘ぎ声を漏らした。
「がっ、ぁ、ぅあああっ……! おっ、奥、当たっ……てぇ……っ!?」
肉棒を引き抜こうとすると、カリハの膣肉はまるで別れを惜しむように竿を強烈に締め付ける。その締め付けに逆らって浅いところまで引き戻した肉棒を、再び奥まで打ち付ける。引き抜いて、打ち付ける。それを繰り返すたびに、カリハの嬌声が洞窟内に響き渡り、俺は彼女を自分のものにしたような錯覚を覚えてより一層興奮を覚えた。
「ぅあっ、お、オマエっ、アタシのこと……孕ませ、ぅぎ!? は、孕ませるつもりか……っ!?」
「カリハはどうしてほしい?」
「オマエ……っ、ん、ぁぐ、うぅ……! い、言わせるつもりかよぉ……っ!」
「カリハの中、俺から全部搾り取ろうとギチギチに締め付けてくるぞ」
「っ……! そうだよ、オマエを気持ちよくさせて、全部搾り取ってやるっ……! ほら、オマエだって我慢できないだろッ! イけ、出せっ、アタシの中に……っ! ていうか、アタシはもう、イクッ……!」
「カリハ……!」
ただでさえ肉棒に食らいついて離れなかったカリハの膣肉が、その締め付けを一気に強める。全てを搾り出してやろう、そういう意思が感じられる締め付けだった。当然、俺もそのつもりだ。雌穴の奥深くまで亀頭を押し付け、カリハの体を抱き締めながら、俺はその惚けた顔にキスをする。カリハもまた、トゲトゲしい牙の間から舌を突き出すと、俺の舌に自分の舌を絡めはじめた。
もうこれ以上我慢はできない。俺は抱き締める力を強めながら、カリハの一番奥にありったけの精という精を注ぎ込んだ。
「んちゅ、はぁ……はぁ……っ、どうだ、全部搾り取ってやったぜ……っ」
「はぁ……はぁ……、確かに、とんでもない締め付けだ……全部持っていかれるかと思った」
「へへっ、アタシもみっともなく乱れちまった……あおいこだな」
肉棒を引き抜いたことで割れ目から溢れ出した精液を、カリハは指で掬い取ってまじまじと眺める。息を乱して胸を上下させているが、彼女の表情はどこか満足気だった。恐らく俺も似たような顔をしているに違いない。つい数秒前まで理性をかなぐり捨てたように貪り合っていたというのに、今や俺とカリハの間には、まるでスポーツで名勝負を繰り広げたライバルのような謎の仲間意識が芽生えていた。
と、興奮が落ち着いてきたことでふと思い出す。俺たちは今2人で夢中になっていたが、そういえばセーラはどうしている?
「ふふっ、私もカリハも、2人とも人間さんに気持ち良くさせられちゃいましたね」
「違ぇよ、アタシとセーラがコイツを気持ち良くさせてやったんだ」
どうやらセーラは、ずっと俺たちの様子を傍で見ていたらしい。そう考えると恥ずかしいな、今更な話ではあるが。
「しかし、流石に疲れたな……2人も連続で相手にしたことなんてないし」
「え? もう終わっちゃうんですか?」
「え?」
すっかり休むつもりでいた俺は、セーラの質問に思わず間抜けな声を出してしまった。
「あんまりですよ……カリハとのあんな交尾見せつけられたら、私もまた発情しちゃうじゃないですか」
「えっ、いや、そうは言っても……って、カリハ!?」
「おいおい、アタシもセーラも、まだ満足してないぜ……? オマエだって、まさかこれで限界じゃないだろ? 疲れたなんて言わせねぇよ」
セーラとカリハは、さっきまでとは逆に俺のことを押し倒すと、それぞれ俺の太ももや腹に舌を這わせはじめる。太ももをつたっていたカリハの舌は次第に股間へと近づき、一気に根元まで咥えこまれたのが感触で分かった。彼女の口から覗く鮫のようなギザギザした歯に少しビビッてしまったが、上手いこと竿に当たらないよう工夫しているのだろう、柔らかい舌の感触だけが強く感じられて、俺は思わず腰が浮きそうになる。
と同時に、腹の方を舐めていたセーラの舌が、今度は胸の方へ上がってきてそのまま俺の右乳首に触れた。不意にぞくっとした感覚が背中を走り、セーラがちろちろと舌先で乳首を舐める刺激がむずがゆくも気持ち良く感じられる。やはりこの2人の人魚、本気でまだ俺から精を搾り取るつもりだ。
「流石に2発も出した直後じゃふにゃちんか……でも、アタシがすぐ元気にさせてやるよ」
「あっ、カリハ……!?」
「私だって……ほら、どうですか? 男の人も、乳首は気持ち良いんですよね……?」
「セーラまで……!」
上と下、二か所を同時に舌が這う。くすぐったいような、気持ち良いような、なんともいえない感覚だ。しかし、こんな可愛い人魚2人に求められるというのは、悪くない。
「人間さん、キスしても……いいですか?」
「ん、んぶっ、ぷはっ……ほぉらやっぱり、まだ大きくなるじゃねぇか」
「んっ、むちゅ、ふぅ、んん……っ、人間さん、もっと私たちのこと……気持ち良く、してくださいね?」
「死にそうになってたところを助けてやったんだ、この程度で嫌とは言わないだろ?」
「さあ」
「ほら」
一緒に楽しもう。そんな2人の誘いに、俺は迷わず身を委ねた。
……そういえば昔、セイレーンという人魚の話を聞いたことがある。美しい歌声で船乗りを魅了して、海底に引きずり込むのだそうだ。そのときは「いくら歌声が綺麗でも海の中に飛び込むなんておかしい」と思っていたが、なるほど、2人の人魚と乱れあっている今なら、船乗りがセイレーンに魅了されてしまう気持ちも分かるかもしれない。
俺とセーラとカリハは、それからどれくらいの時間を「交尾」に費やしていただろう。精液か愛液かも分からないものでぐちょぐちょになりながら、俺たちは欲望のままに互いの体を貪った。外の様子が分からない洞窟の中では、今が朝か夜かさえ分からない。俺たちの交尾が終わったのは結局、誰も彼もが体力を使い果たし、気絶するようにして眠りへ落ちたときだった。
次に目を覚ましたとき、俺はベッドに横たわっていた。洞窟に置いてあった海藻のベッドではなく、ごく普通の布で覆われた何の変哲もないベッドだ。身を起こして辺りを見渡すとそこは海中の洞窟ではなく、どうやら病院の一室のようだった。
勝手に出歩くのもどうかと思ってしばらくそのまま過ごしていると、少し経ってから病室に看護士らしき女性がやってきた。事情を聞くとどうやら俺は、海水浴中に離岸流で沖まで流され半日ほど行方が分からなくなった後、海水浴客が居なくなった日暮れの頃に砂浜で倒れているのを発見されたらしい。俺が居なくなっている間、友人たちは姿を消した俺を大慌てで探していたらしく、看護士の女性によると一時は警察なんかも出てきて捜索活動が行われたという話だ。まあもっとも、その俺が特に怪我もなく無事に戻ってきたので、今はもう解決したことになっているらしいが。
「特に体調不良も見られないですし、問題なさそうですね。まだ早朝なのでちょっと待ってもらう必要はありますが、今日の午前中には帰れると思いますよ」
そう言って病室を出ていく看護士の背中を見送り、俺は再びベッドに寝転がった。
「夢……だったのか?」
海で溺れて、奇跡的に自力で帰ってきた。そう考えた方が納得出来るくらい、人魚という存在はファンタジーだ。この世界には人魚なんて実在せず、あの洞窟での出来事も全て夢だったのかもしれない。現実的に考えれば、そう考えるのが妥当だ。
しかし、あの2人のことは夢とは思えぬほど鮮明に思い出せる。セーラとカリハ、2人の魅力的な人魚。彼女たちの存在は、決して俺の妄想なんかじゃないはずだ。
夢だったのか、現実だったのか、そんなことを考えながら寝返りを打つと、ベッドのすぐ横にある棚の上に見覚えのないネックレスが置いてあることに気が付いた。
「これは……?」
綺麗な貝殻と鮫の牙らしきものがぶら下がっている、いかにも手作りという雰囲気のあるネックレスだ。俺がこんなアクセサリーを身に着けていたことはないが、ここにあるということは俺が持っていたものなのだろう。
またしても病室の前を通りがかった看護士を呼び止めて尋ねてみると、やはりこのネックレスは砂浜に倒れていた俺が首にかけていたものらしい。貝殻と牙、気のせいでなければ、これはセーラとカリハの……。
「……やっぱり、夢じゃないよな」
真偽を確かめる術はないが、2人と共に快楽を貪った生々しい思い出が夢だったとは到底思えない。あまり人間に知られてはいけないと言っていた2人だが、それでも俺を陸に帰すために手を貸してくれたのだろう。きっとこのネックレスは、2人が俺に残した「夢ではない証拠」なのだ。
「またいつか、会えるかな……あの2人」
俺はベッドの上でネックレスを握りしめながら、セーラとカリハの顔を思い浮かべるのだった。
End.