小説「マリア=ノルダール」前編
「あ、あなたは……?」
「先に質問をしたのは私なのだけれど……まあ良いわ、答えてあげる。私はマリア=ノルダール、この森で数百年の時を生きている魔女よ。それで、キミはどこから迷い込んだのかしら?」
「……魔女?」
突然なにを言い出すんだこの女は、と思ったが、この異常な状況に現れた異常な風貌の女だ。むしろ普通の人間だと言われる方が疑わしい。だが……魔女? 俺のイメージだと、魔女と言えばもっとこう……黒いローブを着たよぼよぼの老婆とかそういうイメージなのだが、こんな露出狂みたいな格好の魔女が居るものなのか? いや、実際に魔女を見たことなどないのだから、俺が思っているこのイメージも創作物の影響でしかないのだが。
ひとまず、マリアと名乗った女が本当に魔女かどうかはともかく、このまま沈黙を続けて質問に答えず反感を買うのはよろしくない。そう思った俺は、自分がハイキングの帰りに友人たちとはぐれた経緯を説明し、帰り道を探していることを伝えた。
「……というわけで、この森から出る方法があれば教えてほしいんですが」
「ふむ……なるほど、チェンジリングの標的にされたのね、キミ」
マリアは手に持ったキセルを口に運び、煙を吐き出しながら言った。
「チェンジリング?」
「妖精たちがやるイタズラの一種よ。取り替え子、とも言うわね。あちらとこちら、現世と異界、境界を隔てた別の場所にあるものを文字通り『取り替える』イタズラよ。キミはこちらに引き込まれた側……と言っても、特に理由があって選ばれたわけじゃないわ。妖精は気まぐれだもの、『面白そう』と思ったら深く考えず行動に移してしまうものよ」
「現世と異界……って、じゃあここは」
「そう、ここはキミが住んでいる世界とは少しズレた場所にある異界。普通に歩いているだけじゃ抜け出せないわ、この森に『端』はないもの。私と会えたのは運が良かったわね、下手すれば飢え死にするまで彷徨う羽目になっていたかもしれないわ。……いや、飢え死にならまだマシか」
魔女だとか妖精だとか異界だとか、にわかには信じがたいことばかりだが、現に俺が霧に飲まれてこの妙な森に迷い込んだことは確かだ。いくら小さい山とはいえ、俺がさっきまで居た山ではそれなりの傾斜が続いていた。だがこの森にはそれがない、いつの間にか平坦な地形の上に立たされている。単に山で遭難しただけならありえない話だ。
「どうしたら……どうしたら俺は、元の場所に帰れるんですか?」
「私が手を貸してあげても良いわよ、坊や。もちろん、タダではないけれど」
そう言うとマリアは自分の胸に手を当て、こちらをじっと見つめてきた。俺がどう答えるか、反応を待っているようだった。「坊や」という呼び方には少し引っかかるが、彼女が自称魔女であることを考えると、年齢が3桁にも届いていない人間はみんな「坊や」なんだろう。……本当に彼女は、素直に頼っても良い相手だろうか?
「タダじゃないなら、見返りは……?」
「ひとまず私の家に来てもらおうかしら。どのみちこのまま森の中で一晩過ごすのは得策じゃないわ、命を投げ捨てるようなものよ。今はまだ妖精たちもキミの反応を楽しんでいるけれど、そのうち飽きてきたらもっと刺激的なイタズラを仕掛けてくるかもしれないわ」
「ッ……そ、それは困る……」
「なら私についてくることね。詳しいことは、家に着いてから話すとしましょう。私の家なら妖精も寄り付かないし、危険な森の中とは違って、心地良い椅子も温かい紅茶もあるのだから」
どうやら今の俺に選択肢はないようだ。このまま森の中で彷徨っていても、元の場所に戻れる保証はない。それなら……まだ完全に信用しきったわけではないが、マリアを頼った方が帰れる可能性は高いように思える。
俺はマリアの誘いに対して頷き返すと、満足そうな微笑を浮かべた彼女と共に森の中を歩き始めた。
見通しが悪い霧の中、先導するマリアの背を追いかけること数分。木々が生い茂る森の中に不自然なほど大きく開けた空間が現れ、その中央にこぢんまりとした丸太小屋のような家が見えた。霧にのまれてから初めて見る人工物だ。
「着いたわよ、ここが私の家。中は多少散らかっているけど、我慢してちょうだい」
「いや、まあ……招いてもらって文句を言うつもりはないけど」
薄暗い室内に散乱した、何が書かれているのかもよく分からない紙束の数々。棚には謎の液体が入ったガラスの小瓶がいくつも転がっており、動物の牙か何かを繋いで作られた怪しげなアクセサリーが壁に飾られたりしている。そういうコンセプトの雑貨屋と言われればそう見えなくもないが、ここが「魔女の家」だと思うと、多少なりとも不気味な雰囲気が感じられた。
「それで……元の場所に帰るために、俺は何をすれば良いんですか?」
家に着いたら話の続きをする、その約束だ。俺はマリアに問いかけた。
そんな俺の質問に対し、マリアはもったいぶるようにゆっくりと振り向きながら返事をする。
「せっかちなのね、少し休んでからでも遅くはないわよ? どうせ夜明けを待たないと、今から急いで帰ったところで深夜の山中に放り出されるだけ。そっちの方が危険だわ」
「……夜明けには、元の場所に帰してくれるんですか」
「ええ、約束するわ。それより、ひとまずお茶の時間にしましょう。私も歩き回って疲れちゃったわ。あいにく我が家に客間はないから、寝室で待っていてもらえるかしら。すぐにお茶を用意して持っていくわ」
そう言うとマリアは、リビングを挟んで玄関の反対側にある奥まった場所の扉を指さした。あそこが寝室ということだろう。いくら魔女とはいえ、初対面の男を寝室に通すのは不用心すぎないか……と思ったが、そもそもマリアの服装や態度からしてそういう羞恥心は持っていないのかもしれない。
「じゃあ、お言葉に甘えて……」
俺はマリアに促されるまま寝室に向かい、椅子がなかったのでベッドに腰を下ろした。……座って良いんだよな? わざわざここに通すってことは。
「床に魔法陣が描いてある……」
さっきリビングの棚でも見かけたようなガラスの小瓶が、寝室の棚にも散らばっている。一見すると化粧品か何かのように見えるが、迂闊に触るのは危険だろう。なにせ魔女の家にある代物だ、危険な薬品だったりする可能性も捨てきれない。
落ち着こうにも落ち着けないので、部屋の中をじっと見渡し続けること数分。ティーカップをふたつ載せた盆を持ってマリアが寝室に入ってきたことで、俺の不躾な物色タイムは終わりを告げた。
「…………」
「警戒心があるのは良いことだわ。でも紅茶に毒なんて入れてないわよ、安心してちょうだい」
「いや……普通に猫舌で」
「あら、そう。それは失礼」
熱い紅茶で満たされたティーカップとにらめっこしながら、マリアといくらか言葉を交わす。確かにマリアが悪い魔女なら、この紅茶には毒が盛られているかもしれない。その可能性は確かにあるが、かと言ってこれがただの善意だったときにそれを無下にして反感を買うのも避けたい。ならば「マリアが悪い魔女とは思えない」自分の直感を信じた方が良いだろう。
火傷に注意しながら紅茶を恐る恐る口に運ぶ。……美味い。香りも良いが、これはなんの香りだ? 花のようだが名前が頭に浮かばない。まあ、元々詳しくないので当たり前と言えば当たり前なのだが。
「家の裏で育てているハーブを配合した紅茶よ。毒は入っていないけど、お茶そのものが薬みたいなものね。リラックス効果があって緊張がほぐれるわ」
「なるほど、ハーブティーってやつか……。まだ一口飲んだだけだから、効果があるのかはまだちょっと分からないけど」
「そう? じゃあ、試してみましょうか」
「……え?」
そう言うと、マリアはティーカップをテーブルに置いて右手を自身の胸元に近づけた。そして、おもむろに服と体の隙間に指を引っ掛けると、彼女は余裕のある笑みを浮かべながらそのまま服を押し下げる。
「なっ……!?」
元々胸の谷間がはっきり見えるほど際どかった胸元だが、今や服がめくれて完全に乳房を放り出している。白く豊満で重みを感じるふたつの膨らみと、その先端で確かに存在を主張する綺麗な桃色の乳首が、理性では「見てはいけない」と思っている俺の目を釘付けにさせた。
「毒を盛るなんてとんでもないわ。こういうことはお互い楽しまなきゃ……ね、坊や」
「と、突然なにを……!?」
「対価の話よ。私はキミを元の場所に帰してあげる、その代わり私の望みを叶えてもらう。坊やみたいに体力のありそうな若い男の子は大好物よ……ふふふ、久々のお客さん……たっぷりもてないしてア・ゲ・ル……♡」
ベッドの上、ほとんど裸みたいな格好をしたマリアに押し倒され、身動きを封じられる。いや、おかしい。仮にも俺は並の体格はある成人男性、対するマリアは筋肉質なわけでもなくいかにも女性的な体つきの女だぞ。こんな簡単に押し倒されて、しかも力ずくで振りほどけないなんて。まさか……。
「やっぱり、あの紅茶……!」
「ほら、言った通り。全身の緊張がほぐれてリラックス出来ているでしょう? 大丈夫よ、キミは動かなくても。私がちゃんと気持ちよくしてあげるわ……ふふっ、体から力が抜けると、血の巡りが良くなるのよね」
服から溢れたむき出しのおっぱいを俺の顔に押し付けながら、マリアは慣れた手つきで俺のズボンからベルトを抜き取る。彼女はそのまま俺の股間に手を伸ばすと、ゆっくりと焦らすようにズボン越しの男性器を撫で始めた。
「っ……!」
「坊や、大きなおっぱいは嫌い? ほぉら、触っても良いわよ、そのくらいの力は入るでしょう?」
「お、俺に……何をする気だ……っ!?」
「何って、楽しませてもらうのよ。こんなところに1人で住んでいると、どうしてもこういうことをする機会が少ないの。だからたまに迷い込むキミみたいな子は、私にとって最高のご褒美。ふふ……キミも口ではそう言いつつ、こっちはずいぶんやる気みたいよ?」
マリアはそう言うと、俺の固くなった股間を意地悪そうに人差し指でなぞった。
「私が欲しいのは若々しいエネルギーに満ちた男の精……でも、嫌がる相手から搾り取るのは趣味じゃないわ、こういうのはお互い楽しまないと……」
俺の上に被さるようにしておっぱいを押し当てていたマリアは、そう言いながらベッドから下り、床の上で膝立ちになると、俺のズボンを両手で掴んだ。……いや、ズボンだけじゃない。気がつけばマリアは俺のズボンもパンツも一緒に引き下げている。俺の意思に反してすっかり怒張していたペニスが、狭いズボンの中から解放されてビキビキと血管を浮かせながら存在感を放っていた。
「アハッ……すっごぉ……まさに女を犯すための形だわ」
固くそそり立つ男性器。マリアはそれを指先で撫でると、そっと握って弄ぶ。マリアが身に着けているアームカバーの布地が肌触りの良い感触を伝えてきたかと思えば、アームカバーから唯一露出している指先が触れるたびに、素肌の冷たさが快感の波にメリハリを与えてくる。その手つきは手慣れていて、俺と同じような「犠牲者」が以前にも居たことが容易に察せられた。
「ぅ……くっ……!」
「へぇ、なるほどぉ……キミはここが弱いのね、ふふっ、睨んじゃって可愛いこと……大丈夫よ、そんな怖い顔もできなくなるほど、すぐに気持ち良くさせてあげるから」
「ああっ……!」
未だ体に力が入らない中、ギンギンに勃起した股間の感覚だけがやけに鮮明だった。マリアは手コキと呼ぶにも弱々しい力加減でペニスを撫で続け、イタズラっぽい笑みを浮かべている。焦らしているのだ、この魔女はわざとこうやってもどかしい刺激を与えている。
そう思った次の瞬間、俺はマリアがわざとらしく舌を出してヨダレを垂らす姿を見た。それはまるで、獲物が疲れ果てた瞬間を狙って襲いかかる蛇のようで……。
「んむっ」
直後、マリアは大きく口を開いて俺のペニスを咥え込んだ。唾液まみれの舌が絡まり、指先の冷たさとは打って変わって生暖かい粘膜が竿全体を包み込む。それだけでも十分な刺激だが、マリアはそこで止まらなかった。舌を動かし、吸いつき、しゃぶり尽くすようなストロークを繰り返して、一向に刺激を加える手を緩めない。
「ぁ、うぁ……っ!」
「ん、むぐっ……うふ、どうかしら? 私のおクチは。これでもまだ嫌がるかしら?」
「っ……!」
「ほぅら、また食べちゃうわよ。……んぐっ、はぁっ、顎が外れちゃいそうだわ……これはちょっと、期待しちゃうかも……っ」
じゅぷじゅぷと音を立て、マリアが竿を舐り上げる。彼女は時折こちらを見上げるように視線を向け、その甘えるような上目遣いがより一層俺の興奮を煽った。ハーブティーの効能で体の力を抜かれ、強引に押し倒され、俺が襲われているはずなのに、まるで手厚い奉仕を受けているような満足感が押し寄せてくる。
ペニスにしゃぶりつくマリアの口から唾液が溢れ、太ももの辺りを温かい液体が伝っていく。彼女が言う「リラックス効果」の影響なのか、俺の陰茎は普段よりも明らかに太く大きく怒張していた。深々と根本まで男根を咥え込んでいるマリアの口からはときどき「うぐ」とか「おえ」とか苦しそうな呻き声が漏れ、よく見るとこちらを見上げる瞳にはじんわりと涙が滲んでいる。だが、それでも彼女はフェラチオをやめなかった。まるで彼女自身が、その苦しさを楽しんでいるように。
「う、ぅぶ……おぇ、っ……はぁ……っ! はぁ……ああっ、危ない危ない、喉の奥を塞がれて……っ、坊やの凶悪なおちんちんに、殺されるところだったわ……っ」
口元を唾液まみれにしたマリアは、ようやくペニスから口を離して乱れた息を整えた。元々の肌が白いせいだろうか、薄暗い寝室の中でも彼女の顔が赤くなっている様子は手に取るように分かり、彼女の興奮が落ち着くどころか昂っていることもありありと伝わってくる。
「……お前を満足させたら……ちゃんと帰してくれるんだよな?」
「当然よ、約束は守るわ……ちゃんと満足させてくれるなら、ね」
「……それなら、俺も好きに楽しませてもらおうか」
「ふふ、そうね、一緒に楽しみましょう……坊や」
そうだ、最初から選択肢なんてない。この魔女に頼らなきゃ帰れないんだ。なら、抵抗も躊躇も意味がない。そっちがその気なら、こっちも好きなようにヤらせてもらうだけだ。
《後編につづく》
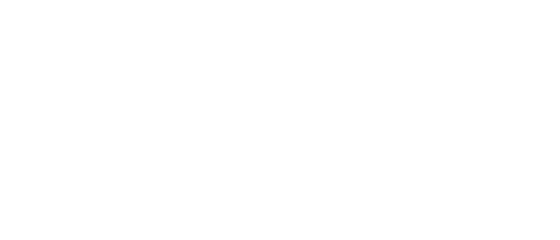
![リアルボディ 魔性のやわちち マリア=ノルダール[引取無料]丨大人のおもちゃとアダル](https://www.wildone.co.jp/review/wp-content/uploads/luxe-blogcard/f/f3800ceac1657cf3534c7495b5bfc45f.jpg)







